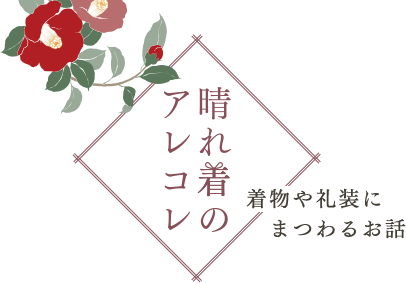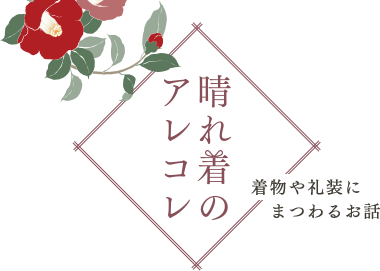目次
赤ちゃんの無事の誕生に感謝し、健やかな成長を祈願して行われるお宮参り。その際、赤ちゃんに着せる衣装が産着(祝い着、掛け着)ですが、着せ方がよく分からないという声も多く聞かれます。それゆえ、間違った着せ方をしている方、残念な見映えになっている方もチラホラ…。そこでここでは、着せ方のNG事例を具体的にご紹介。意外に多くの方がやってしまっている内容なので、よくチェックして失敗回避に役立ててくださいね。
産着(祝い着、掛け着)とは、どんなもの?
赤ちゃんが産まれて最初に行う儀式的な行事に「お宮参り」があります。そして、このお宮参りの際に赤ちゃんに着せる着物が産着(祝い着、掛け着)です。ここではまず、産着がどんな特徴や意味を持つもので、どのような着せ方をするのか解説します。

お宮参りをする赤ちゃんの正装が「産着」
お宮参りには本来、赤ちゃんをその土地の氏神様に参拝させて、新しい氏子として祝福をうけるという意味がありました。ですが現代では、赤ちゃんが無事に産まれたことを感謝し、健やかな成長を祈る行事として行われています。神様を祀る神聖な場所で執り行う行事ですから、当然、服装も改まった様式で臨む必要があります。赤ちゃんに着せる産着(祝い着、掛け着)はそのための衣装であり、誕生後はじめて着る正装=晴れ着です。
なお、赤ちゃんに産着を着せる際には、内着や帽子、よだれかけなど、他にも必要なアイテムがあります。レンタルの場合は必要なものが一式セットになっている場合が多いですが、赤ちゃんの両親や兄妹姉妹が着たものを利用する場合や、新たに購入する場合は、足りないものがないように注意して準備を進めてください。また、お宮参りの衣装は、必ずしも産着でないといけない訳ではありません。ご家庭によっては、セレモニードレス、ベビードレスと呼ばれるような洋装を選択されるケースもあります。
▼関連記事
「産着」は、赤ちゃんを抱っこした人が上から羽織る
産着(祝い着、掛け着)は赤ちゃんのための衣装ですが、赤ちゃん本人に着付ける訳ではありません。産まれたばかりですから、赤ちゃんは基本的に抱っこの状態です。そのため着せ方としては、抱っこした人の上から赤ちゃんを覆うように産着を羽織らせ、その人の背中側で付属の紐を結んで固定するという方法になります。
ただ、注意したいのはこの紐の使い方、結び方です。この点を誤っている方が意外と多く、産着の美しい柄が隠れて見えなかったり、紐の結び方が苦しそうに見えたり、残念な見映えになっているケースが散見されます。一人目のお子様で、お宮参りもこれがはじめて…という方にとっては、分からないのも当然のことですが、この機会にぜひ覚えておきましょう。以下の関連記事内に、着せ方を丁寧に紹介した動画がありますので、ぜひ参考にしてください。
▼関連記事
産着(祝い着、掛け着)の着せ方でよく見られるNG事例
ここからは、産着(祝い着、掛け着)の着せ方のうち、多くの方が誤りがちなNG事例を具体的にご紹介します。どうすれば正しい着せ方になるのか、対処方法も解説しますので合わせてご確認ください。
NG事例01)紐が袖に通っていない

一般的に、産着(祝い着、掛け着)の内側には、汗や垢などの汚れがつくのを防ぐための襦袢を重ねて着ます。この襦袢にも産着にも、胸のあたりに左右1本ずつ平たい紐が付いており、着用時にはこの紐を重ねて、左右それぞれ肩から袖口へと通して使うのが正しい方法です。ところが、紐を袖に通していないNGケースがよく見られます。この状態では左右の袖が身体の前側に垂れてきて、産着の背面に描かれている柄を隠してしまいます。せっかくの美しい柄が見えないのが残念なばかりか、見た目の印象もだらしなく映ります。また、両方の袖がヒラヒラと視界を遮って邪魔になることもあるため、動作には注意が必要です。なお、産着によっては紐がついていないケースもあります。この場合は紐だけを単体で購入して、産着に縫い付けて利用してください。
◆着せ方のポイント
襦袢と産着の紐を重ねたら、右側の紐は右の袖へ、左側の紐は左の袖へ、それぞれ通します。こうしておくと、紐を結んだ際に袖も一緒に身体に固定され、邪魔になることがありません。
NG事例02)紐を首の後ろで結んでいる

産着(祝い着、掛け着)および襦袢の紐は、右紐、左紐それぞれを、赤ちゃんを抱っこした人の背中側へ回して結びます。正しい着せ方になっていれば、背中の肩甲骨のあたりに結び目ができるはずです。ところが、結び目が首の後ろにあり、食事エプロンのようになっているNGケースが見受けられます。これだと、紐を結んでいる人の首が苦しそうに見えてしまいますし、実際、首の後ろ1点に負荷が集中することになるため、時間の経過とともに苦しさを感じる場合もあるでしょう。また、産着にシワが寄ってしまい、背面に描かれた柄が見えづらくなってしまう恐れもあります。
◆着せ方のポイント
赤ちゃんを抱っこした状態で、優しく包み込むように産着を掛けます。赤ちゃんの顔とは反対側の肩に産着の一方を掛け、もう一方を赤ちゃんの顔にかからないように掛け、左右の紐を抱っこした人の背中で結びます。結び目は肩甲骨のあたりに作ると良いでしょう。こうすると肩から斜め掛けにしたような状態になり、紐がずり落ちにくくなります。
NG事例03)産着の下から襦袢が大きくはみ出している

産着(祝い着、掛け着)を着用する際は、生地が汗や垢で汚れないよう、内側に襦袢を重ねます。レンタル衣装の場合は、産着と襦袢が一体化しているものもあり、あまり失敗はありませんが、これらの重ね方がきれいにできていないと、産着の下から襦袢がはみ出してしまうことがあります。襦袢が多少見えてしまうのは問題ありませんが、大きくはみ出した状態だと見た目に美しくないばかりか、だらしない印象を与えかねないので、羽織る前にチェックしましょう。
◆着せ方のポイント
産着と同様に、襦袢にも紐がついており、この両方の紐は右側同士、左側同士を重ねて袖に通します。この際、襦袢の紐が産着の紐よりも緩くならないように注意してください。緩みが大きいと、内側の襦袢がたるんでしまい、産着からはみ出しやすくなります。
着せ方のポイントを押さえれば、初めてでもきれいな見映えに
ここでは、産着(祝い着、掛け着)を美しく着せるための方法を、手順を追って解説します。ポイントは大きく2点。「事前に紐を袖に通しておく」「斜め掛けの要領で羽織らせ、紐を背中で結ぶ」ができれば、初めて産着を着せるママ、パパでも上手にできるはずです。
ポイント01)事前に紐を袖に通しておく
産着の内側に襦袢を重ねたら、産着と襦袢についている紐を2本まとめて左右それぞれの袖の中に通します。襦袢の紐が緩んでいると、産着からはみ出しやすいので、少し強めに引いておきましょう。
ポイント02)斜め掛けの要領で羽織らせ、紐を背中で結ぶ
背後から産着を着せかけ、一方を赤ちゃんの顔と反対側の肩に掛け、もう一方を赤ちゃんの顔にかからないように掛け、抱っこした人に羽織らせます。左右の紐を背中側に回し、肩甲骨のあたりで蝶々結びをします。背後から見た際、左右の紐が水平に一直線ではなく、斜め掛けのような状態になっていると安定します。

▼関連記事 以下のページで着せ方の手順やポイントについて詳しくご紹介しています。
最後に
はじめてお宮参りをするパパママにとっては分からないことも多く、間違った着せ方になってしまうケースも多い産着(祝い着、掛け着)。ですが、先述したポイントさえ押さえておけば、大きく失敗することはありません。赤ちゃんにとって、お宮参りは一生に一度。産まれてはじめての大切な晴れの日ですから、正しい着せ方をしっかりマスターして臨みたいですね。
晴れ着の丸昌 横浜店では、男の子用、女の子用それぞれ、多彩な色柄の産着を取り揃えております。ネットレンタルサイトであれば、全国どこへでも配送可能。必要なもの一式をセットで手軽にご準備いただけます。また、実物を見て選びたいという場合は、横浜店にお越しくださいませ。たくさんの衣装を実際に手に取りながら、じっくりとお選びいただけます。